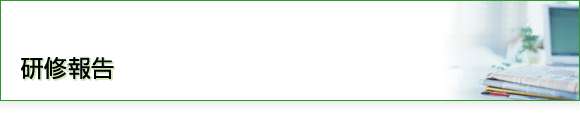H28年 12月 3日(土) 「管理者研修会」
-
会場 札幌ホテルノースシティ 参加者 39名 内容 講義 「看護管理に必要なこと」 講師 特定医療法人北仁会 旭山病院
看護部長 齋藤 香奈恵 先生 - 道央圏以外からの参加者もあり、看護管理に関するニーズの高さが伺えました。また、対象が管理職ということもあり、50%以上が10年以上の精神科経験を持っていました。参加者それぞれ70%が「学べた」「分かりやすい」「役立つ」と評価されています。満足度も高く、意見・感想で「現場で役立てられる内容だった。」「疑問を直接聞けて良かった。」という声が聞かれています。意見・情報交換の場の提供を望まれている声があるなか、今後の参加継続に関しては、研修内容の充実が必須であり、さらなる検討が必要であると考えます。
H28年 11月 19日(土) 「ストレングスモデル研修会」
-
会場 函館渡部病院 参加者 55名 内容 講義 「ストレングスモデルと看護実践
-ストレングスマッピングシートを使った対話をはじめよう-」講師 聖路加国際大学大学院 精神看護学
教授 萱間 真美 先生 - この研修会では、学べた、分かりやすかったというアンケート結果でした。以下、参加者の抜粋になりますが、「現場ですぐ使えそう。」「 実際に活用してみたいと思わせる研修でした。」「精神科の経験が少ないのでとても分かりやすいお話でよかったです。」「福祉の現場の人とグループワークをしてみたい。」「現場ではつい患者さんとの対話する時間を持っていないことに気づきました。」「ストレングスモデルを自分の対話の手段に役立たせていきたい。」などの感想が聞かれています。
H28年 10月 29日(土) 「看護研究発表会」
-
会場 札幌ホテルノースシティ 参加者 115名 内容 看護研究発表 「第1群・第2群・第3群」 トピックス 「業務改善報告」 - 発表件数は9席と昨年に比べ減少しましたが、参加者は昨年を上回る人数であり、看護研究発表会への関心の高さを感じました。本年度の開催では初めて、午前の講義を入れずに研究発表のみとして一つの会場で行うことですべての演題に参加できるように配慮させていただきました。アンケート結果では90%以上から「学べた」「分かりやすかった」「満足した」と回答されています。参加者からは様々な感想をいただいておりますので、次回開催へ向けた検討事項として真摯に受け止めたいと考えております。また、研究発表としての場として、会場での活発な意見交換を期待する声がありました。次年度はフロアからのさらなる質疑応答を期待したいと願い、活性化に向けて考えていきたいと思います。
H28年 10月 16日(日) 「発達障害研修会」
-
会場 札幌医療リハビリ専門学校 参加者 142名 内容 講義 「児童思春期の発達障害」
「大人の発達障害」講師 医療法人社団 倭会
こころとそだちのクリニック むすびめ
院長 田中 康雄 先生 - 募集定員を大幅に超えた参加者数であり、関心・満足度が非常に高い研修会であったと感じました。今回の研修では、児童思春期・大人の発達障害に関心が高かった様子です。研修の実際では、講師の方の体験談も交え、参加者にとっては笑いもある楽しい内容であったと評価されています。また、患者というカテゴリーだけではなく、現在子育て中の方やこれから子育てを迎える方々に対しても、子供とのかかわり方をあらためて学ぶ機会になった印象がありました。今回の研修が学びと深みになったこと、また様々な形で感謝の思いが聞かれた好評の結果からは、次年度の開催継続が期待されています。
H28年 10月 1日(土) 「WRAPを学ぶ研修会」
-
会場 旭川トーヨーホテル 参加者 24名 内容 講義 「WRAP〜元気回復行動プランの実際にふれる」 講師 コープランドセンター認定アドバンスレベルWRAPファシリテーター
地域活動支援センターはるえ野センター長
増川 ねてる 先生 - 今回、参加者のほとんどが『WRAPとは何か?』を知らなかったこともあり、紹介から始まり、グループワークを通し体験するという構成で行われました。講師の方は当事者という立場からWRAPに出会い、現在ではその体験をアドバンスファシリテーターという立場において全国で活躍されている方です。その、当事者の体験という説得力のある話から、看護者向けに患者のリカバリーに大切なキーコンセプトを分かりやすく説明されていました。自分のリカバリーや危機的状況から脱するためのツールとして、その人らしく生きていくためになにが有効であることかが話されています。グループワークでは実際に体験したことで興味を持った参加者が多かったことはアンケート結果からも垣間見えます。楽しく研修会を受けることができた機会でした。
H28年 9月 24日(土) 「毎日行うCVPPP研修会」
-
会場 帯広とかちプラザ 参加者 24名 内容 講義 「医療における暴力とその要因」 講師 国立研究開発法人
国立精神・神経医療研究センター病院
杉山 茂 先生 - 道東ブロックでの開催でしたが、道央、道北からも参加がありました。CVPPP(包括的暴力防止プログラム)は単なる合気道、抑制術ではなく、暴力を起こす人をネガティブにはとらえず、適切な介入をすることにより「援助する」という考え方です。講義の中では、暴力事件の実態や暴力への介入スキルとしてのリスクアセスメント、段階的なディエスカレーションなど、実践を交え分かりやすい研修でした。アンケートからも、学べた、分かりやすかった、役立つ、と高い評価でした。CVPPPの概要を学ぶ目標は達成できたと感じています。しかし、現場では暴力に出会ったら焦りやアセスメント不足、介入目的や手法のズレなどにより暴力に至る可能性もあります。したがって、暴力防止に対する理解を深め対応していくことが必要であると考えます。今回の研修参加者の精神科経験年数は幅広く、精神科看護を行っていくうえで必要性を感じる研修会でした。次年度も繰り返し学習が必要な研修会であると考えます。
H28年 9月 10日(土) 「精神科における医療安全研修会」
-
会場 札幌ホテルノースシティ 参加者 101名 内容 講義 「精神科病院における医療事故の現状と基本的対応」
「再発防止策の検討と評価 −臨床的視点を中心に−」講師 社会医療法人財団松原愛育会 松原病院
医療安全支援局長 兼 医療部長
川田 和人 先生 - アンケートの結果からは、参加者の医療安全への関心の高さが伺えました。また、参加者にとっては難しく感じたり、わかりやすいと感じたりした幅がありましたが、参加者の経験年数などによっても変化することだと思いました。今回、基本的なことから分析・事例と多くの内容で進められ、どれも良い内容でしたが、全体的にやや時間不足の印象がありました。近年の精神科において、医療安全への認識が高くなってきていることを踏まえると、今後も医療安全についての研修会を続けることが必要と思います。参加者からの意見にもありましたが、経験年数などを考慮し数回に分けて行ったり、全般的な内容を抑えつつ重点的に学べるものに分けたりするなど、背景に合わせた様々なバリエーション考慮し、検討しても良いかと感じました。
H28年 8月 6日(土) 「認知症研修会④」
-
会場 札幌リハビリ専門学校 参加者 68名 内容 講義 よくわかる認知症看護シリーズ 第4回
「認知症の地域・社会背景について学ぼう」
午前「認知症看護を取り囲む社会背景・家族看護」
午後 グループワーク「シリーズまとめ 認知症看護を語ろう」講師 特定医療法人北仁会 旭山病院
認知症病棟看護師長 南 敦司 先生 - 認知症研修会(全4回)が終了致しました。4回目は主に家族看護と退院支援に焦点を当てた研修となりました。認知症の社会調整、家族看護のあり方、社会資源をふまえて、具体的なかかわりや看護師の役割についての講義でした。また、合わせて退院支援について、社会保険制度の仕組みや介護保険制度サービスなどを実際の事例をとおした講義がありました。午後は全4回の研修を振り返り、グループワークで意見交換を行い、研修終了となりました。同じテーマで全4回シリーズでの研修は北海道支部として初めての試みでしたが、参加者からは好評の声を多くいただけました。
H28年 7月 30日(土) 「精神科身体合併症看護研修会」
-
会場 釧路市幣舞ふれあいホール 参加者 39名 内容 講義 「最近の身体合併症の傾向 精神科身体合併症看護について」
「フィジカルアセスメント 精神科でよくみられる身体合併症について」講師 医療法人社団橘会 多度あやめ病院
精神科認定看護師
看護師長 小粥 奈緒美 先生 - 道央ブロックの所属の参加者を中心に、道央や道北からの参加者もみられました。各施設でも、長期入院や高齢化、認知症の増加があることから、関心が高かったことが伺えました。午前の講義は「最近の身体合併症看護について」、午後は「フィジカルアセスメント」「精神科でよくみられる身体合併症について」で、さらに少人数での各施設の取り組みや課題などを共有したグループワークが取り入れられていて、参加者からは好評でした。事例をもとに精神科看護の特徴をふまえ、一人で抱え込まずに周囲のスタッフに相談することが大切であること、まずは患者様に関心を向けること、患者様をよく知ることで小さな変化を見逃さないことが、早期発見や早期介入につながることを再認識しました。次年度以降も他のブロックでの開催を前向きに検討したいです。
H28年 7月 23日 (土) 「退院調整に関する研修会」
-
会場 特定医療法人富田病院(函館) 参加者 51名 内容 講義 「精神医療に求められるこれからの退院支援」 講師 日本精神科看護協会 業務執行理事
東海大学健康科学部看護学科
准教授 吉川 隆博 先生 - 参加された多くの方々から、学べた、分かりやすかったというアンケート内容で、概ね好評の結果でした。参加者からは、基礎知識、地域支援との関係性、退院支援のポイントなどが学べ、有意義な研修の様子が感じられたことが読み取れます。退院を調整する方法や仕組みについて、より詳しく学びたいといった声がきかれ、また、退院調整をとおして、精神医療が向かう、今後の方向性や多くのことを感じ取った研修会でもあり、各参加者の今後の活躍に役立って欲しいと考えています。次回の要望としてはアウトリーチやフィジカルアセスメント、家族看護などについての研修要望が聞かれました。
H28年 7月 2日(土) 「認知症研修会③」
-
会場 札幌リハビリ専門学校 参加者 70名 内容 講義 よくわかる認知症看護シリーズ 第3回
「認知症看護のNGを学ぼう」
午前「行動制限最小化と認知症看護」
午後 グループワーク「行動制限を体験しよう」講師 特定医療法人北仁会 旭山病院
認知症病棟看護師長 南 敦司 先生 - 「認知症看護のNGを学ぼう。行動制限最小化と認知症看護」が開催されました。午前は認知症周辺症状(BPSD)で入院される認知症患者様に対してのNGや行動制限を行うことのデメリット、行動制限最小化を目指すことでの治療効果について講義がありました。午後は様々な身体拘束を体験し、グループワークを通して意見交換を行いました。参加者からは、「患者さんの立場に立って看護することの大切さをあらためて感じました。」「現在、行動制限しないようにスタッフとともに考える事が出来た。」「スタッフの意識が大切だが、もっと上の管理者が理解していかないと進まないと思う。」「分かりやすく病棟でも取り入れてみたい。」「いろいろな意見が聞けて参考になった。」といった様々な意見が聞かれました。
H28年 6月 4日(土) 「認知症研修会②」
- 1回目と同様に、「分かりやすかった」「役立つ」といった意見が多くきかれています。今回は、カンフォータブル・ケア、アクティビティ・ケアについての講義、午後は日常生活にある「快」「不快」を五感それぞれについて考えるグループワークを行いました。どちらも、高齢者看護、認知症看護を行う上で有効な技術であるため、講義の中ではその知識を深めるとともに具体的な技術についても学んでいきました。午後のグループワークでは午前の講義を元にグループワークを行い、認識を深めました。研修を進めていくうえで自己の課題も明確になった様子です。「今後のケアでは患者が快と思えるような態度・接し方で援助していくよう改めて気づけたので良かった。」「また次回楽しみに来ようと思っています。」「グループワークでいろいろと話すので、他の人の意見も聞けてよかったです。」「あっという間に時間が過ぎ『快』でした。」などの感想が聞かれています。
| 会場 | 札幌リハビリ専門学校 | ||||||
| 参加者 | 66名 | ||||||
| 内容 |
|
H28年 5月 28日(土) 「初任者研修会」
-
会場 札幌医療リハビリ専門学校 参加者 76名 内容 講義 「精神障害を学び理解する 〜病態生理から人生(生活)まで〜」 講師 株式会社 ここから
村本 好孝 先生 - 精神科の学びの理解についてなど、講義全般で「分かりやすい」「役立つ」が大半を占めていたアンケート結果でした。精神科初任者の多くは、精神科看護のファジーな部分に共通して悩みを抱いている場合がありますが、講師は非常に幅広い知識を、初任者でも理解しやすいように身近な事例や体験談を交えながら説明されていました。参加者の理解度の評価も高く、満足度も高い評価を受けています。また、この研修会は毎年一定数の需要があり、新人だけではなく10年以上の経験年数がある参加者も多いことから、来年度以降も企画継続の必要があると考えています。参加者からも、「毎日ただ勤務をこなしていたが、少し興味がわいてきた。」「精神科に異動し、わからないことばかりだが、明日から仕事に役立てられるよう勉強したい。」「研修で改めて患者に対する考え方を学べ、明日より実践でそうです。」などの声があり、意欲向上の糧となる研修会であったと感じました。
H28年 5月 7日(土) 「認知症研修会①」
-
会場 札幌リハビリ専門学校 参加者 71名 内容 講義 よくわかる認知症看護シリーズ 第1回
「認知症を理解しよう」
午前「認知症ってどんな病気・認知症総論」
午後「四大認知症を理解しよう・認知症疾患別各論」
ロールプレイ「疾患別特徴に応じた対応方法」講師 特定医療法人北仁会 旭山病院
認知症病棟看護師長 南 敦司 先生 - 「認知症ってどんな病気?」という内容から、今年度の認知症研修会が始まっています。総論・各論の内容について「どちらかといえば」という表現を含めると、100%の方が分かりやすい、役立つと評価されています。興味深く受講できたこと、認知症を理解し看護を行う重要性をあらためて感じたこと、日々の業務の中で効果的な対応に結び付けたい、と言った思いが聞かれています。ロールプレイや、グループワークといった内容で理解を深め、お互いの思いを共有、また共感できた様子が感じられました。
H28年 4月 22日(土)、23日(日) 「看護研究研修会」
-
会場 札幌ホテルノースシティ 参加者 38名 内容 講義 「具体的な研究方法とまとめ方① -事例研究と質的研究-」
「具体的な研究方法とまとめ方② -アンケート調査と介入研究‐」講師 札幌医科大学保健医療学部看護学科
准教授 澤田 いずみ 先生 - アンケート結果では、プログラム内容で個人差はあるものの、講義内容ではそれぞれの内容について「分かりやすい」と評価されました。期待度、満足度も高く、全体ではおおむね好評であったと感じています。参加者からは、研究症例外にもアドバイスが欲しい、研究の進め方が明確になったことで、自主的に進めていくことができる、といった感想が聞かれていました。また、看護研究については年間で2〜3回の開催を要望する声が聞かれています。今回は、一日半という時間で開催致しましたが、今後は内容含め様々な方向からの検討が必要と考えます。